平成29年度 子ども・若者活躍推進事業取組発表会・県央地区 ~青少年育成運動活性化研修会~
趣旨
青少年育成団体が県の助成を受けて行う、青少年が地域を知り、愛着や誇りの思う気持ちを育む取組事業の発表や地域で伝承芸能活動に取り組んでいる青少年の芸能披露、各団体が取り組む青少年育成事業の意見交換を通じて、青少年育成活動への意識高揚を図るとともに、今後の地域における青少年育成活動の活性化を図ることを目的とする。
主催
公益社団法人青少年育成秋田県民会議・秋田県
共催
青少年育成にかほ市民会議
開催日
平成30年2月18日(日) 13:30~15:30
開催場所
にかほ市象潟公民館 ホール
参加者
44名


平成29年度助成団体による取組発表
「能代JCドリームカップ」
発表者
一般社団法人 能代青年会議所
次世代育成委員会委員長 佐藤 裕之 氏 (さとう・ひろゆき)
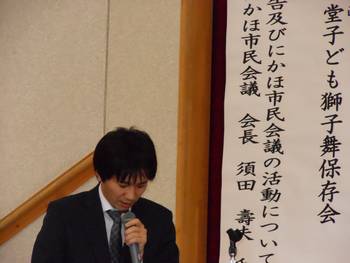

- 能代青年会議所青少年育成委員会の活動について。
- この事業を通じて、子どもたちの体力を向上させるとともに、規律を尊ぶ態度、思いやりの心を培うこと、地元地域スポーツであるバスケットボールの有意性を再認識してもらい、子どもたちの交流、愛郷心を育むことを目的にしている。
- 7月16日の実施当日は、ミニバスケットボール・スポーツ少年団139名をはじめ、秋田ノーザンハピネッツ、能城工業高校バスケットボール部を含むスタッフ、合わせて222名が参加し、コーチングや模擬試合、スポーツ精神についての学び、ミニバスケットボール大会を実施した。
- 事業の成果として、参加者である子どもたちはもとより、保護者達からも反響が大きく、来年度以降も開催してほしいという声が多かった。
「カポエイラ体験会&カポエイラフェスティバル」
発表者
カポエイラ・ヘジョナル・ジャパン秋田
代表 後藤 良 氏 (ごとう・りょう)


- ブラジルの伝統武術カポエイラを、現地講師を招へいして県内の保育・幼稚園で体験会を実施。「カポエイラフェスティバル」と称したイベントの実施を通して幼少期の運動神経の向上やカポエイラを通じた他国人との交流によりグローバルな考えを持つきっかけになるよう努める。
- 「地域愛溢れる青少年育成事業」は、秋田が誇る伝統文化を活かし、地域を愛する心を育みながら、子どもたちが人と人とのつながりの大切さを学ぶ場を創出していく必要があると考え実施した。
- 幼児を対象とした体験会は、8月・9月に秋田市内を中心に大仙市、潟上市の14保育・幼稚園を訪問し実施、述べ810の園児が参加した。9月10日に秋田市土崎のポートタワーセリオンで開催したフェスティバルには80名が参加、見学者は約200名であった。
- 事業の成果として、多くの子どもたちがにカポエイラを体験してもらうことができた。フェスティバルを通してカポエイラの普及・広報活動にもつなげることができた。
子ども伝承芸能発表
大日堂子ども獅子舞
出演団体
大日堂子ども獅子舞保存会 (にかほ市象潟町) にかほ市立上浜小学校児童 7名



市町村民会議の活動発表・報告
「青少年育成にかほ市民会議の活動及び内閣府主催、北海道・東北ブロック研修会報告」
発表者
青少年育成にかほ市民会議
会長 須田 壽夫 氏 (すだ・としお)
- 市民会議の今年度のメイン事業である「中学生リーダー研修会~ふるさとの一員として~」を紹介する。目的は、リーダーとしての自覚を高め、企画運営能力や統率力向上を図る。生徒の交流を通して連帯意識の高揚、ふるさとについて学び、幅広い視野をもち社会に貢献できる人材育成としている。参加者は、にかほ市内3中学校に加え、姉妹町である宮城県松島町の松島中学校からの5名で20名が参加。8月8日~9日の1泊2日で実施した。市内施設見学、リーダーとしての心構えの講義、高校生ボランティア同好会の講義・交流などの内容で実施され、リーダーとしての資質の向上、交流の輪が深められた。
- 内閣府主催、「子供・若者育成支援のための地域連携推進事業~北海道・東北ブロック研修会~」は、10月11日に青森市において開催され、約150人が参加し、秋田県からは8名が参加した。
- その内容の主なものを報告する。はじめに内閣府から「子供・若者育成支援施策について」、推進法やそれぞれの取組施策について講話があった。次に事例検討会が4分科会あり、それぞれの参加者が午前、午後に選択1分科会に参加する方式で行われ、午前は、第1分科会「若者による地域づくり(まちづくり、まちおこし等)」に参加した。実践発表は「一般社団法人『三陸ひとつなぎ自然学校』の取組」と題して、法人代表の伊藤聡氏が発表した。午後は、第4分科会「逸脱行為・少年非行の動向と立ち直り支援」をテーマに、山形保護観察所統括保護観察官の小野旬氏が事例発表した。最後に、全体会が行われ、4分科会のコーディネーターが各事例発表内容や課題について、それぞれ報告が行われた。

